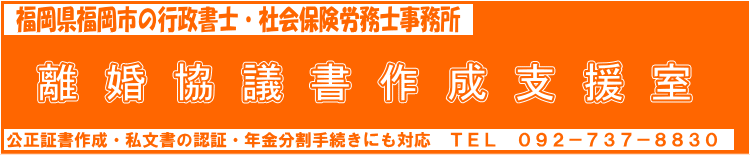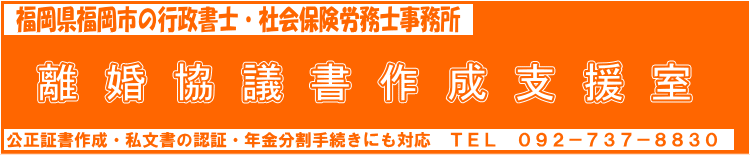福岡県 福岡市 離婚協議書を公正証書で作成 養育費・財産分与・慰謝料・年金分割手続・親権・子供との面接など離婚条件を公正証書で作成。福岡県福岡市の行政書士・社会保険労務士平塚事務所が離婚協議書・公正証書作成・年金分割手続をサポート・支援。
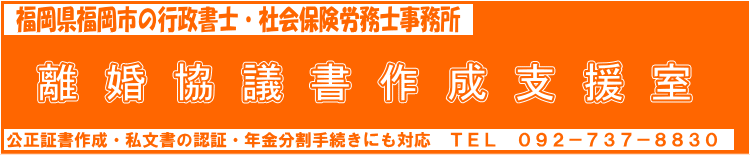 |
|
|
|
|
|
《離婚時年金分割手続き完全代行サポート≫
◆年金分割制度とは◆
離婚時の年金分割とは、将来に受け取ることのできる老齢厚生年金の算定の基となる会社で勤務し給与から支払った厚生年金保険料の納付記録(標準報酬総額)を分割することです。
夫婦のうち、厚生年金保険料の納付記録(標準報酬総額)の多い方から少ない方にの記録を移すというイメージをしていただければと思います。
○分割の制度について○
【合意分割】
以下の条件に該当したときに、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができます。
・婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること
・当事者間の合意又は裁判手続きにより按分割合を定めたこと。
*当事者間の話し合いで合意に至らない場合は、当事者間の一方の求めにより、裁判所が按分割を定めることができます。
・請求期間(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
按分割合とは、分割対象となる婚姻期間中における当事者双方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)合計額のうち、分割を受けることによって増額される側の分割後の持ち分割合のことです。
【3号分割制度】
以下の条件に該当したときに、国年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。
・婚姻期間中に平成20年4月1日以後、の国民年金の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録があること
・請求期間(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
*3号分割制度については、当事者双方の合意は必要ありません。
*合意分割の対象期間に3号分割の対象となる期間が含まれている場合、合意分割を請求した時点で3号分割の請求があったものとみなされます。
○分割請求期限の原則○
分割請求の期限は原則として、次に掲げる事由に該当した日の翌日から起算して2年以内です。
(1)離婚をしたとき
(2)婚姻の取り消しをしたとき
(3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき
◆協議すべき内容◆
年金分割手続きを行うために当事者間で協議をすべき内容です。
◎離婚届を提出する時期
◎按分割合について
*情報通知書をもとに協議します
◎合意内容を文書にする際、公正証書にするか、私文書の認証で行うかどうかの選択。
◆年金分割手続きの流れ(合意分割)◆
1.年金分割のための情報提供の請求
情報提供は、年金分割請求手続をするにあたり、事前に必要な情報を当事者へ提供するものです。これは、「年金分割の割合」が自由に決めることができるものではなく、法律で定める範囲内になるように決めることとされているため、その範囲や分割の対象となる期間等の情報の提供を受けられるようにしたものです。
(情報提供の請求の方法)
◆請求する場所
・住所地を管轄するの年金事務所
◆必要な書類
・年金分割のための情報提供請求書
(添付書類)
①請求者のご本人の国民年金手帳、年金手帳又は基礎年金番号通知書
②婚姻期間等を明らかにすることができる書類
(戸籍謄本、当事者それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書又は当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書)
③事実婚関係にある期間に係る情報提供の請求をする場合は、その事実婚関係を明らかにすることができる書類
地域の年金事務所により必要な書類が異なることがあります。事前に確認をしておくことが大切です。
2.「年金分割のための情報通知書」の交付
①2人が一緒に請求をした場合は、それぞれに交付します。
②1人で請求をした場合は、次のとおりです。
・離婚等をしているときは、請求した方とその相手方に交付されます。
・離婚等をしていないときは、請求した方のみに交付します。
3.当時者間の話し合い
年金分割の割合等について、当事者間の話し合いにより合意したときは、次に掲げるいずれかの書類によりその合意した内容などを明らかにして、年金分割の請求手続きを行うことになります。
これらの書類に関する手続は、公証役場で行うことになります。
●公正証書の謄本
あるいは
●公証人の認証を受けた合意書(私文書の認証)
*年金分割の割合について、当事者間の話し合いでは合意が成立しないときは、家庭裁判所におけるし審判手続きなどの裁判手続を利用して年金分割の割合を定めることができます。
4.年金分割の請求
当事者間で年金分割に合意し、公正証書等を作成した後は年分割の請求です。
請求先は年金事務所になります。
◆必要な書類
・「標準報酬改定請求書」
(添付書類)
①請求者のご本人の国民年金手帳、年金手帳又は基礎年金番号通知書
②婚姻期間等を明らかにすることができる書類
(戸籍謄本、当事者それぞれの戸籍抄本、戸籍の全部事項証明書又は当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書)
③事実婚関係にある期間に係る情報提供の請求をする場合は、その事実婚関係を明らかにすることができる書類
④年金分割の割合を明らかにすることができる書類
◆当事者の合意により、年金分割の割合について定めたとき
・公正証書謄本
あるいは
・公証役場で公証人の認証を受けた合意書(私文書の認証)
◆裁判所における手続により、年金分割の割合について定めたとき
審判(判決)の場合
・審判(判決)書の謄本又は抄本及び確定証明書
調停(和解)の場合
・調停(和解)調書の謄本又は抄本
地域の年金事務所により必要な書類が異なることがあります。事前に確認をしておくことが大切です。
5.「標準報酬改定通知書」の交付
按分割合に基づき当事者それぞれの厚生年金の保険料納付記録の改定が行われ、改定をした後の保険料納付記録が、当事者それぞれに通知されます。
◆ご準備いただくもの◆
●個人を証明するもののコピー(双方)
*運転免許証、パスポートなど
●年金手帳(双方) 基礎年金番号がわかるもの
・ご依頼主は現ぽをお預かり、配偶者の方はコピー
●年金特別便、年金定期便のコピー(双方)
*お手元にございましたらお願い致します
*年金の加入状況がわかるもの(勤務した会社名などがわかるもの)
●住民票(本籍地のあるもの)
*戸籍謄本が取得できる方は戸籍謄本でも大丈夫です
●印鑑証明書(双方)
「事実婚の期間がある場合」
●事実婚にある期間を証明できる書類のコピー
【離婚成立後】
●離婚成立後の住民票(本籍地の記載のあるもの)
●戸籍謄本(離婚成立後のもの)
*当事務所での取得代行も可能です
◆サポート料金◆
①情報通知書の請求から、合意書の作成、公証役場での手続き、年金分割の請求までの代行
総額 : 5万5千円+実費
(実費について)
・公証役場での手数料(公正証書あるいは私文書の認証)
・戸籍謄本等の必要書類の取得手数料
・郵送料・切手代
②3号分割制度のみ(平成20年4月1日以降の3号被保険者の期間のみを対象)
総額 : 3万5千円+実費
(実費について)
・戸籍謄本等の必要書類の取得手数料
・郵送料・切手代
◆当事務所(行政書士・社会保険労務士)に依頼するメリット◆
年金分割手続きのスタートから手続き完了までをサポートします。
●年金事務所への書類作成及び届出代行
・情報通知書の請求書類の作成・提出
・年金分割の請求書の作成・提出
●公証役場での書類作成の代行
・年金分割のための合意書の作成
*公正証書、私文書の認証どちらにも対応します
●必要書類の取得代行
・住民票や戸籍謄本(離婚前後)の取得
・その他の必要書類の取得
無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。
電話:092(737)8830 事務所までの地図
◆お問い合わせ・お申し込み お問い合わせは無料です。
◆事務所での面談相談のお申し込み 30分:3000円
◆無料メール相談 回答の返信は48時間以内が目安です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|